こんにちは、ラッコです。
今回は、Netflixにて配信中の「レナードの朝(原題:Awakenings)」を鑑賞しました!
原作は神経科医オリバー・サックスの実体験を元にした小説で、いわゆる名作映画です。
嗜眠性脳炎の患者を演じるロバート・デ・ニーロをはじめとしたキャスト陣の表現力がとても高く、自然でリアルな演技に強く引き込まれました。
題材は少々重めですが、観る前と観た後では自分の人生が少し違って見えるくらい、強く心に残る映画でした。
早速ご紹介していきます!
・名作ヒューマンドラマを観たい方
・優しい気持ちになれる映画が好きな方
作品概要
| 題名 | レナードの朝(原題:Awekenings) |
| 公開年 | 1990年 |
| 監督 | ペニー・マーシャル |
| キャスト | ロバート・デ・ニーロ(パーキンソン病に苦しむ男性/レナード・ロウ) ロビン・ウイリアムズ(医師/マルコム・セイヤ―) ペネロープ・アン・ミラー(レナードが恋した女性/ポーラ) ジュリー・カブナー(看護師/エレノア・コステロ) ルース・ネルソン(レナードの母) |
| 原作 | レナードの朝(オリバー・サックス著)※1970年初版のノンフィクション |
︎
あらすじ
研究室を追い出され、就職先を探していたマルコム・セイヤー医師。
臨床経験がないにも関わらず、ブロンクスのとある精神科病棟に採用される。
配属された慢性神経症病棟では、ほとんど何の反応もない、他者の手助けがなければ生活ができない患者がたくさん入院していた。
セイヤー医師は持ち前の探究心から、彼らに誠実に向き合い、現状が少しでも改善しないかを熱心に研究し始める。
慢性神経症の患者たちの様子を観察していく中で、彼らに僅かながら反射反応が残っていることに気が付き、その症状がパーキンソン病に似ていることを発見したセイヤー医師。
パーキンソン病の新しい治療薬(L-ドパ、別名レボドパ)を試しに最も重症の患者・レナードに投薬すると、なんとレナードが30年の時を経て身体機能を取り戻し目覚めたのである。
レナードが目覚めたことをきっかけに、セイヤー医師はレナードと同様の症状を持つ他の患者にも投薬を行った。
患者たちは次々と”目覚め”ていくが、彼らを待つ未来とは————————————
映画の注目ポイント
セイヤー医師の患者への誠実な向き合い
セイヤー医師が配属された病棟は、立って前へ進む、食事をする等、最低限の動き以外は何の反応も見せない慢性神経症の患者たちばかり。しかし、働いている医師や看護師は患者たちを治療する気がなく、ただ生きていくのに最低限のお世話をするだけです。
それでも、セイヤー医師は一人ひとりに誠実に向き合い、改善のためにどうしたらよいかを熱心に考えます。
他者からの評価など気にせず、目の前のことを諦めない姿勢は、観ていて心を打たれます。
レナードの心の成長
レナード自身が”目覚め”た当初、鏡を見て年老いた自分の姿に驚くシーンがあります。慢性神経症によりレナードの人生が”止まって”いる間も、身体の「時」は進んでいたことに気づかせられるのです。
再び進み始めた時間の中で、レナードが急速に学び、成長する様子は、失った時間を取り戻そうと、貪欲に様々なことを吸収し、また、人生を謳歌しているようにも見えます。
こうした時間を経て、レナードとセイヤー医師は「患者」と「担当医」でなく、次第に友達のような関係へと発展していきます。
感想・考察
これから鑑賞される方へ(ネタばれなし)
事前知識なしに鑑賞しましたが、始まってすぐみるみるストーリーに引き込まれました・・・
「現代の映像に慣れているせいで、画質の違う昔の映像を観るのに抵抗がある」という方も世の中にはいらっしゃるかと思いますが、そんな苦手意識をものともしない、非常に引き込まれる映像と物語です。
「パーキンソン症状」に踏み込む
本作は、「パーキンソン症状」に対し、過去に人類がアプローチした実話を元にしています。
主人公のレナードが患っていた嗜眠性脳炎は今もなお根本的な治療法は見つかっていないくらいなので、1960年代当時は今以上に対応が難しかったのではないでしょうか。
映画の舞台になっている1969年は、まだパーキンソン症状の原因がドーパミンの低下によるものだと分かってすぐの時代。
作中で登場する新薬L-ドパの投薬も実験的なものだったそうなので、今まで昏睡状態だった患者たちが目覚めた瞬間は、まるで奇跡に近いものだったのだろうなと思います。
ロバート・デ・ニーロの名演は必見
そして、この映画を観た誰もがロバート・デ・ニーロの名演に圧倒されることと思います。
「嗜眠性脳炎の患者」という難しい役どころにも関わらず、主人公レナードの人生を本当にただ横で撮影していたかのような、素晴らしい演技でした。
相当病気について勉強し、研究を重ねてこの作品に臨んだのだろうというのが伝わってくる圧巻の演技で、観ているだけでその裏の努力が感じられました。
セイヤー医師の優しさ溢れる人柄
ロビン・ウィリアムズ演じるセイヤー医師に対する周囲からの印象が、徐々に変わっていくところも見どころの一つです。
冒頭のセイヤー医師は、研究者気質でなんとなくとっつきにくい雰囲気を醸し出していて、他の医師たちと距離があるような印象。
しかし、一人ひとりの患者と実直に向き合う中で、レナードはもちろんのこと、他の患者たちや看護師エレノアとも関係を築いていきます。
セイヤー医師の根底に真面目で優しい性格があったからこそ、患者たちを目覚めさせることに成功したのだろうなと思います。
二人の関係性
セイヤー医師とレナードの関係性が深まっていくにつれて、両者の表情が映画の前半から中盤以降豊かになっていく様子が観ていてとても魅力的でした。
研究熱心で対人関係が苦手なセイヤー医師と、病気のせいで30年間の時間を失ったレナードにとって、お互いの存在はすごく大切なものだったと思います。
双方の演技が本当に素晴らしく、映画にどっぷり入り込めました。
深く考えずに選んだ映画でしたが、121分以上の満足感があり出会えてよかったと思える作品でした。
ここからネタバレあり ※未鑑賞の方は注意
重たい題材で、非常にいろいろなことを考えさせられました。
患者たちが目覚めていたひと夏の短い期間は、本人たちにとってどんな意味をもたらしたのか・・・
レナードの目覚め
11歳のときに病気を発症して以来、30年間も半昏睡状態にあったレナード。
自分の人生の、しかも10〜30代という一番多くのことを経験するであろう時期がすっぽり抜けてしまうなんて、考えただけで恐ろしいことだなと思います。
L-ドパによって目覚めてからのレナードは、まるで新しい人間に生まれ変わったかのように生き生きとしていて、観ていてすごく温かい気持ちになりました。
もし自分がレナードと同じ立場だったら、30年の時を失ったという事実に絶望し、せっかく目覚めたとしても何も手に付かない自信があります・・・
ポーラとの出会い、レナードの変化
ポーラに一目惚れをしたレナードは、投薬治療を受け動けるようになった他の患者たちとのお出かけを一人断り、お見舞いに来ていたポーラを病院内の食堂のランチに誘います。
今までセイヤー医師や母であるロウ夫人をはじめとした周囲のサポートありきの生活をしていたレナードが、なんと自らの意思で決断し、行動に移したのです。
レナードがやっと自分自身の人生を生きることができているような気がして、個人的にこの場面はすごく印象に残りました。
このときのレナードは、いわゆるパーキンソン病の症状が一切なく、セイヤー医師に自分の考えを伝えて行動できるくらいまでに回復していました。(もしかしたら恋の力による影響もあったのかも・・・?)
ポーラからも「どうして入院しているの?」と聞かれるほど病気であることを感じさせない様子で、レナード自身も病気のことは忘れているかのようでした。
レナードの気づき
ポーラに恋をしたことをきっかけに視野を広げ、生きていることのすばらしさに気づいたレナード。
居ても立っても居られなかったのか、夜中にもかかわらず病院へセイヤー医師を呼び出し、人生の尊さを熱弁します。
突然呼び出され何事かと駆けつけたセイヤー医師は、熱く語るレナードに拍子抜けした様子。
レナードは30年間意識がなかったからこそ、目覚めてからの生活で生きていることのすばらしさをより強く感じたのだと思いますが、それにしても夜中に呼びつけてまで言うことか?と思ってしまいますよね笑
しかし、そんなセイヤー医師を気にすることなく、レナードは自身の気づきを嬉しそうに話し続けました。
 らっこ
らっこなんと朝の5時まで話し続けたレナード・・・!笑
何時間も付き合ったであろうセイヤー医師には最大級の優しさを感じます・・・
気持ちの変化と挫折
人生は自由ですばらしいものだと認識したレナードは、だんだん「みんなと同じように自由に外に出たい」と思う気持ちが強くなっていきます。
患者は一人では外に出られず、付き添いが必要です。それに納得がいかないレナードは、セイヤー医師や病院に対し、「ほかの人たちと同じように、自分も好きなときに外に出ていろいろな経験をしたい」と申し出ました。
レナードは、病院の理事たちが集まる場に自ら赴いて、はっきりと自分の考えを伝えにいきます。
しかしながら、病院からは一人での外出の許可は下りず、レナードの提案は却下されてしまいます。
レナードはまだ目覚めたばかりで病気が完治したかはわからない状況なので、病院としてはまあ真っ当な判断ですよね・・・
しかし、レナードは却下された事実を受け入れられず「散歩に行く」と強引に病院の出口に向かい、警備員や複数の医師らに抑え込まれてしまいます。
このときの抵抗できないレナードの悲しげな表情には、自らの意思が受け入れられなかったことによる悔しさや、これだけ回復しても自分は自由に生きられないんだと実感したことによる苦しみが表れているような気がして辛い気持ちになりました。
反抗期のレナード
以降、納得できないレナードは、共に入院している他の入院患者らを扇情し、徒党を組んで不品行な行いをし始めます。
患者たちの前で饒舌に演説するレナードは、これまでにないくらい気持ちが昂っている様子で、目覚めてからの穏やかで優しい雰囲気とは正反対です。
自分の欲を抑えられず、病院側の大人たちの言うことを聞かなくなったレナードは、反抗期に突入した子どものようにも見えました。
また同時に、レナードの体には再び緊張や痙攣などの症状が出始めます。
完全に収まったように見えていた症状は、悲しいことに、やはり完治したわけではなかったのです。
パーキンソン症状が再発したレナードは、それでもなお、しばらく抵抗する様子を見せていましたが、症状が収まらないことを受け遂に観念し、とうとうセイヤー医師に助けを求めます。
そのころには症状がかなり進んでしまっており、病院側の「外出を許可しない」という判断は結果的に正しかったと分かってしまいます。
病気に向き合うレナード
だんだんと症状が悪化していき苦しむレナードは、セイヤー医師に自分の姿をカメラに記録するように言います。
自分病気を治すための研究材料として残そうと考えたのだと思います。
レナードに今までなかった注視発作が出たときにもカメラを向けるセイヤー医師。
しかし、レナードが発作により苦しむ姿は非常に痛々しく、とても回せないとセイヤー医師はカメラを止めようとします。それでも「映せ!」「学べ!」と主張するレナードは、「自分のため」と言いつつも、後世の自分と同じ症状を持つ患者たちのために、自らが実験台となっているようにも見えました。
レナードの決意とポーラの優しさ
この発作を経て、レナードはポーラに別れを告げることを決心します。
レナードが自分の病気はもう治らないと自覚した上での行動だと思うととても辛くなる場面です・・・
病院の食堂で痙攣の症状が止められないレナードは、悲しそうな表情をしながら「会うのは、これきりに…」と告げ、ポーラと握手をして立ち去ろうとします。
しかしポーラは、握ったレナードの手をそっと自分の腰に回し、食堂でそのまま静かに踊り始めます。
終始痙攣していたレナードの症状が一時的に止まり、レナードの悲しそうな表情は徐々に安心した表情に変わっていきます。
ポーラの優しさ・暖かさが表現された心温まるシーンであると同時に、心の距離が近づいた二人がもう二度と会えないかもしれないと思うととても悲しくなりました。
奇跡の時間がもたらしたもの
間も無くして、本人が予期していた通り、レナードは再び固まってしまいます。
ひと夏の奇跡のような時間が幕を閉じた瞬間でした。他の患者たちも徐々に目覚める前の状態へ戻ってしまいます。
レナードが再び固まってしまってから、セイヤー医師は、目覚めた直後の生き生きとしたレナードが映されたフィルムを見て過去に想いを馳せます。
自分の行動によって「命を与えてまた奪った」ことを悔やみ、つらい気持ちを吐き出すセイヤー医師。
看護師エレノアは「命は与えられ、奪われるものよ」とセイヤー医師を慰めます。
L-ドパの投薬から始まった一連の出来事を、セイヤー医師は「奇跡の夏」だったと話します。
L-ドパで患者たちを治療することはできませんでしたが、彼らの目覚めによって、人と人との繋がりが新しく生まれ、生きることの喜び・仕事や楽しみ、友情や家族などが何より大切だということを、レナードだけでなくセイヤー医師自身も気付かされました。
再び眠ってしまった患者たちにとって、一時的にでも目覚めたことは幸せだと言えることだったのか、それともまた元に戻るくらいなら目覚めない方がよかったのか、当人たちの視点でどちらが正解だったのかは映画の中では語られていません。(もちろん人によるところもあると思いますが)
しかし、レナードをはじめとした患者たちが目を覚ましたあのひと夏は、それぞれの時が進み出し自分の人生を生きることができたあの時間は、たとえ僅かな時間だったとしても尊く価値のあるものであったとわたしは思います。
わたしたちが生きている中で当たり前だと思っていることは、レナードたちにとっては欲しくても手に入らないものなのかもしれません。自分の人生や今ある生活を大切にしよう、と思わされる映画でした。
まとめ 難病に立ち向かう、実話を基にしたヒューマンドラマ
少し古い映画ではありますが、今観ても全く色褪せない引き込まれる作品でした。
一つ一つのシーンが作り込まれていて、登場人物の心情の変化などが丁寧に描かれているのがよかったです。
そしてなんといっても俳優陣の演技がすごくリアルで、何一つ違和感がないのがすごいなと思いました。
非常に満足度が高く間違いなく名作なので、気になった方にはぜひ観ていただきたいです!
ヒューマンドラマが好きな方には特に強くおすすめします。
それでは。
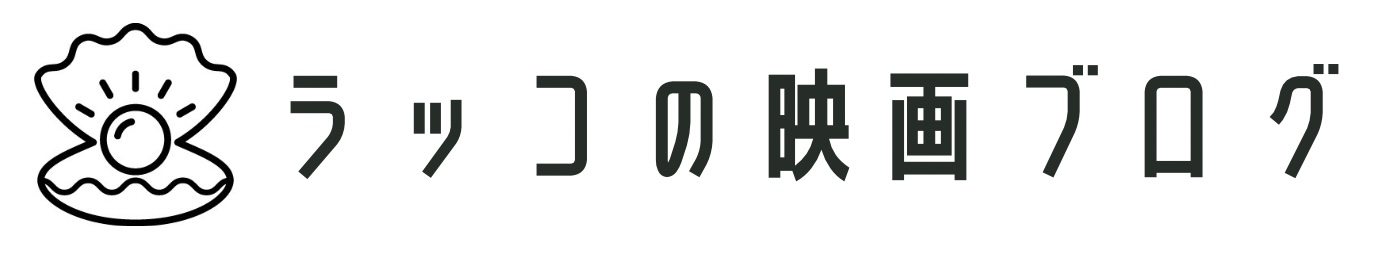
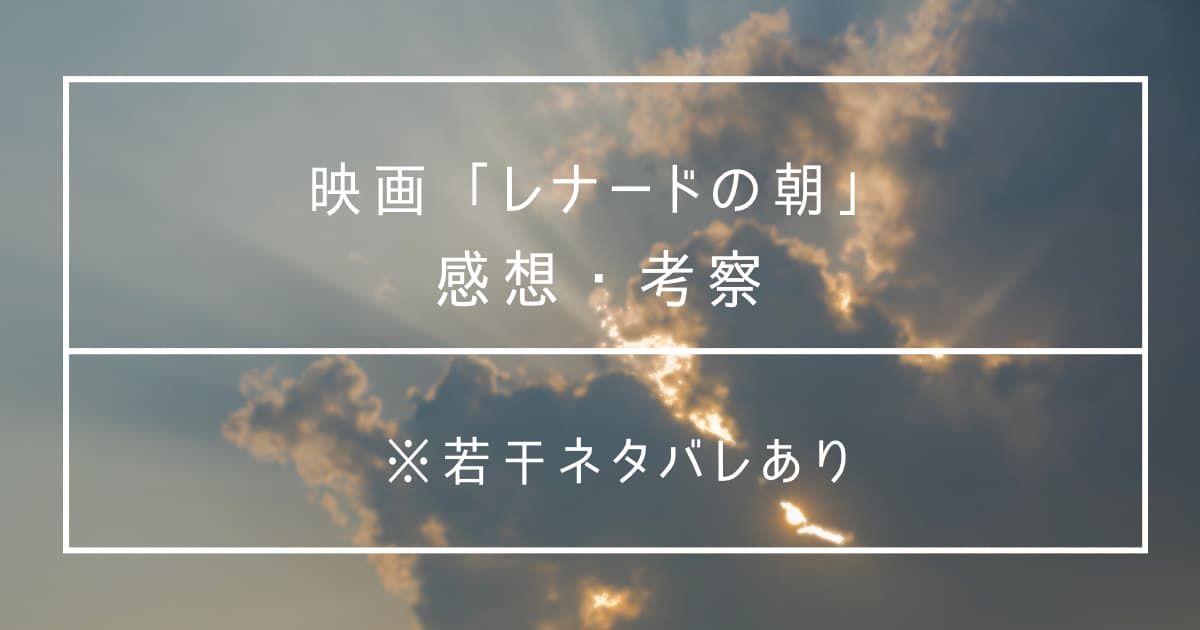

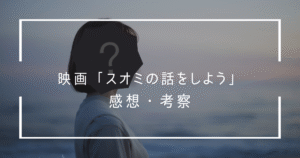

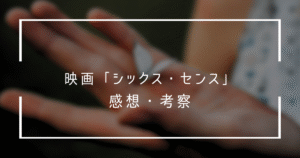
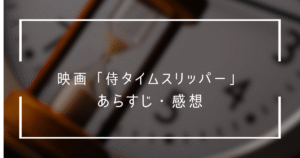
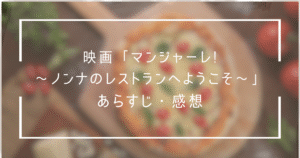
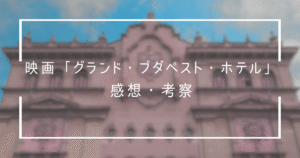
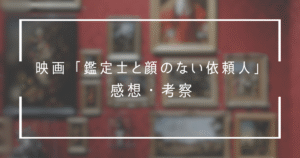
コメント