こんにちは、ラッコです。
今回は「関心領域 The Zone of Interest」を鑑賞しました。
ナチスドイツ政権下の象徴とも言えるアウシュヴィッツ強制収容所の隣に住んでいた家族を描いたお話ということで公開当初から話題になっていたこちらの作品。
Amazonプライムの見放題で配信が開始されたと知り鑑賞してみましたが、とても丁寧に作り込まれた、予想以上に深いメッセージ性のある良作でした。
個人的に気になったポイントである“過剰に保護されるライラック”については、記事の後半でかなり深掘りして解説しています。
同じように気になっている方は、ぜひこちらから読んでいただきたいです。(もっと詳しく知りたい方はこちらから読んでいただくことをおすすめします)
早速ご紹介していきます!
作品詳細
| 題名 | 関心領域 The Zone of Interest |
| 公開年 | 2023年 |
| 監督 | ジョナサン・グレイザー |
| キャスト | クリスティアン・フリーデル(ルドルフ・ヘス役) ザンドラ・ヒュラー(ヘートヴィヒ・ヘス役) |
| 公式サイト | 映画『関心領域 The Zone of Interest』オフィシャルサイト |
概要
空は青く、誰もが笑顔で、子どもたちの楽しげな声が聞こえてくる。そして、窓から見える壁の向こうでは大きな建物から煙があがっている。時は1945年、アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいた。第76回カンヌ国際映画祭でグランプリに輝き、英国アカデミー賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞、トロント映画批評家協会賞など世界の映画祭を席巻。そして第96回アカデミー賞で国際長編映画賞・音響賞の2部門を受賞した衝撃作がついに日本で解禁。
マーティン・エイミスの同名小説を、『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』で映画ファンを唸らせた英国の鬼才ジョナサン・グレイザー監督が映画化。スクリーンに映し出されるのは、どこにでもある穏やかな日常。しかし、壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音、建物からあがる煙、家族の交わすなにげない会話や視線、そして気配から着実に伝わってくる。その時に観客が感じるのは恐怖か、不安か、それとも無関心か? 壁を隔てたふたつの世界にどんな違いがあるのか?平和に暮らす家族と彼らにはどんな違いがあるのか?そして、あなたと彼らの違いは?
映画「関心領域 The Zone of Interest」オフィシャルサイトより
感想・考察
これから鑑賞される方へ(ネタバレなし)
覚悟はしていましたが、想像以上に壮絶で、重たくずっしりと心に刻みつけられた映画でした。
淡々と描かれる日常の中に現れる影
ストーリーとしては大きな抑揚はなく、ただ淡々とヘス家の日常が描かれるのみ。隣接した壁の向こうに強制収容所があるということを除けば、それは平和的で穏やかな日常です。
しかし、その日常の中に垣間見えるホロコーストの影。
ヘス家の人々は、それらを本当の影として、まるで見向きもせず、ただそこにあるものとして生活を送っていますが、映画を観ている側の私たちのほうがその影に強く意識を向けてしまいます。
いくら家族が幸せに過ごしていても、塀の向こう側で行われている卑劣で残虐な行為は、死体の焼却により発生する煙、ユダヤ人たちのうめき声や叫び声を通してはっきりと伝わってきます。
映画を通してはわかりませんでしたが、人間が焼けるにおいや腐敗臭なども、ヘス家ほど近い場所であれば感じられたのではないでしょうか。
 頭のいいらっこ
頭のいいらっこホロコーストには大虐殺という意味があって、ナチス・ドイツがユダヤ人に対して行った組織的な迫害行為のことをいうよ
当時のドイツ人の価値観
ヘス一家の様子を見ていると、その行動や会話の節々から当時の価値観が見えてきます。
彼らにとって「ユダヤ人」という人種は蔑まれる対象であったこと、殺されて当たり前の存在であったこと。
作中で直接的な説明はなされていませんが、ヘス家を通すことでそれらの感覚をリアルに、半ば強制的に感じさせられました。
もちろん戦時中という特殊な状況下であり、ナチスドイツによる洗脳的な側面もあったかと思いますが、軍人ではない人々の間にも「ユダヤ人は悪で罰するべき対象だ」という共通認識が浸透していたという事実に衝撃を受けました。
映画の中で恐ろしいと感じたポイントの一つです。
歴史を学ぶことの意義
日本ではよく「戦争が起きたという歴史を忘れてはいけない」という言葉をよく聞きますよね。
この「関心領域」という作品は、まさに歴史すなわち過去の過ちをなぜ忘れてはいけないのかを教えてくれる映画だと感じました。
当時のドイツの人々と今この世界で生きている私たち、どちらも同じ人間です。
彼らがユダヤ人を不当に扱ったように、人間は同じ種であるはずの別の人間を加虐してしまう資質を持っていると考えると、同じ生物として自分自身も他人事ではありません。
それに気がついたとき、自分が当時のドイツの人々と同じ感覚を持っていないか不安になるとともに一気に怖くなりました。
自分が正しいと信じていることや考え方など、全ての感覚を疑いたくなります。
美しい映像から伝わるもの
そして、これだけ多くのことを考えさせられる本作ですが、なんと映像自体に残酷な描写は全くありません。
アウシュヴィッツを題材にした映画では非常に珍しいのではないでしょうか。
それどころかむしろ牧歌的というか自然豊かで綺麗とも言える画面描写が続き、明るい雰囲気すら感じさせます。
だからこそ、その平穏に流れる生活の中に登場する「焼却炉」「荷(人間の死体)」という物騒な言葉や、「靴から洗い流される血」「川に流される遺灰や燃え残った骨」といった観客の想像を掻き立てるようなぞっとする描写が色濃く際立ちます。
話が進めば進むほど、この環境下で塀の向こう側を気にせず楽しげに暮らしているヘス家の異常性を実感しました。
ホロコーストについて事前に調べておくと◯
本作を鑑賞するまで、ホロコーストについてはぼんやりした知識しかなく、恥ずかしながら意識的に知ろうとしたことすらありませんでした。
実際わたしのように歴史の教科書程度の内容しか知らない、という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回「関心領域」を鑑賞して、深い知識がなくともおおよそ内容は理解できたのですが、やはり当時の情勢を知っていればより細かな描写の意味がわかって楽しめたのではないかと感じました。
意図を汲み取れなかった部分は鑑賞後に調べ、さまざまな記事を読み漁りましたが、それが結果的にナチス・ドイツについて学ぶきっかけになりました。
歴史を知る第一歩におすすめの映画
歴史を知ることはもちろん大切ですが、残虐な描写が苦手なのに無理をしてまで受け止めるのは個人的には違うかなと思っているので、ホロコーストについて知る第一歩として本作は非常におすすめです。
ここからネタバレあり ※未鑑賞の方はご注意
独特な映像作り
まず印象に残ったのは、まるで当時の生活をそのまま切り取ったかのようなリアルな映像です。
本作のひとつの特徴である、ふんわり柔らかい雰囲気を纏った、明るくも暗くも見える不思議な質感の映像は、撮影用のライトを使用せず、光源は自然光や部屋の天井についている電球のみで撮影されたそう。
強い光がないためか画質が鮮明すぎず、そのぼんやりした雰囲気が、現代ではなく過去のお話であるということを感じさせます。
また、本作ではヘス家のいたるところに固定カメラを設置し、撮影は無人で行われたそうです。
カメラの操作は地下で行い、撮影時にいるのは演者だけ。そして、撮れた映像を後から並び替えて、作りたいストーリーを組み立てたそうです。
まるで本当の家族がそこに住んでいるかのような自然な映像は工夫の上に成り立ったもので、リアルさを追求するためにかなり慎重かつ丁寧に作られたことが感じ取れました。
映像に関連して、もう一つ特徴的だったのは夜のシーンです。
セットとしての照明を使わない撮影のため、夜のシーンはサーモグラフィが用いられました。
突如として現れる白黒の映像の中で、一人の少女が作業場のような場所で土にせっせとりんごを埋めていきます。
この彼女は、アレクサンドラ・ビストロン・コロジエイジチェックという実在するポーランド人をモデルとしており、当時12歳だったアレクサンドラはレジスタンスの一員として、収容所のユダヤ人にこっそり食べ物を与えていたそうです。
この映画の中に登場する唯一の良心が彼女でした。
少女が作業場で見つけた楽譜を持ち帰り自宅のピアノで演奏するシーンがありますが、この曲は実際にアウシュヴィッツに収容されていたヨセフ・ウルフというユダヤ人によって書かれた曲だそうです。
少女のピアノの音に合わせて、字幕として表示される歌詞は、本作で唯一受け取ることができるユダヤ人の気持ちです。
そういった意味でも、このサーモグラフィによる夜のシーンはとても印象に残りました。
音の重要性
もう一つ、この映画に欠かせない要素として、「音」があります。
平和的で幸せそうな家族の映像を通して、私たちがユダヤ人が虐殺されていた現実を知ることができるのは、ほとんど音による表現だけでした。
目に映るのは「自然の中でヘス一家が楽しそうに過ごしている穏やかな風景」なのに、聞こえてくるのは「怒号」「銃声」「叫び声」「機械音」など平和とは真逆の恐ろしい音。
ヘス家の一番の異常性は、この音とともに生活を送ることを一切気に留めていなかったことだと思います。
庭で遊んでいるときはもちろん、家の中にいるときですら届いてくる壁の向こう側からの音。
聞こえているはずなのになぜそれを無視することができたのか。
ヘス家が幸せに暮らせた理由
ヘス家の人々は、徹底的に壁の向こう側で起きていることに対して無関心でした。ユダヤ人が虐殺されていることは、自分たちにとってまるで関係がないのです。
ルドルフ・ヘスは収容所の所長であり、収容所で起きていることの実行者です。
子どもたちには隠していたようですが、妻のヘートヴィヒは収容所内でたくさんのユダヤ人が殺され焼かれていることを知っています。
実態を知っていてもなお、自分たちだけに関心を向け幸せに暮らすことができたのは、当事者意識が全くなかったからなのだと感じました。
「見て見ぬふりをしていた」という言葉を使いたくなりますが、それは少し違う気がしていて、彼らは「見た上で見ないふりもしていなかった」のだと私は思います。
見ないふりをすることで現実から目を背けていたのではなく、彼らにとって壁の向こう側で起きていることはただの日常で当たり前のことだったのではないでしょうか。
気づいてはいるけれど、自分には関係のないことだから気にならない。
壁の向こう側で起きていることは、見ないふりをするまでもない些細なことで、そんなことよりも自分たちの生活が大切なのです。
本当に家族みな幸せだったのか
しかし、まだ赤ちゃんである三女がずっと泣き続けているのは、次女が夢遊病のような症状を患っているのは、ラストシーンで体調は万全のはずのルドルフ・ヘスが嘔吐をしたのは、結局壁の向こう側に無関心で居続けることができなかったからなのだと思います。
妻のヘートヴィヒは、収容所の真横にあったあの家で暮らすことが、自分だけでなく子どもを含めた家族みんなにとって幸せであると考えていたようですが、夫のルドルフ・ヘスや一部の子どもたちは、はっきりとは語られていませんが、収容所の横で暮らしていたがための影響を少なからず受けていたのだと感じました。
ヘス家に遊びにきたヘートヴィヒのお母さんも、あの環境に耐えられず途中で勝手に帰ってしまいましたしね・・・



夫の転勤が決まっても、絶対に今の家に住み続けることを譲らないヘートヴィヒの頑固さにはとても驚いたよ
【重要】「優生思想」と「農本主義」
ナチスは当時、「血と土」というスローガンを掲げていました。
ここで言う「血」とは、当時ナチスに支持されていた「優生思想」に基づくもので、アーリア人の血統を表します。
優生思想とは、簡単にいうと「優れた遺伝子を残し、劣った遺伝子を排除」しようとする思想です。遺伝性の病気や障がいを持つ人々などを劣っているとし、強制的に不妊手術を行った断種法もこの思想から生まれたものです。
(断種法はかつて日本でも行われていましたね)
当時のドイツでは、「”アーリア人”という民族こそが優れた人種」だという考え方が広がっていました。
ナチスは、ドイツ人を「アーリア人」の一種であるとした一方で、ユダヤ人やロマ族などのアーリア人以外の民族を「非アーリア人」とみなし、その考えは反ユダヤ主義を正当化するために利用されました。
もう一つの「土」は、ドイツの大地=国土のことを表します。
当時のドイツには、都会での生活を離れ、牧歌的で自然と調和した、かつての生活に回帰しようとする”アルタマーネン”という民主主義的な考え方を持つ集団が存在しました。
このアルタマーネンに属していた”ダレ”という人物は、ナチスに入党後「種族の血と土着性」が重要だと主張しました。
「血と土」とは、”アーリア人という優れた人種”によって、耕され保護された土地が、ドイツという国の基盤となり、その地で労働をする農民こそが、真の貴族になりうるといった、ダレが普及させた”農本主義的なイデオロギー”で、ドイツの美しい自然に囲まれた農村で、アーリア人が子孫を繁栄させることで、ドイツ人はより純粋で優れた血統となると考えたのです。



ヘス夫妻もアルタマーネンに所属していて、そこで知り合ったみたい
ヘートヴィヒの自然愛と保護される「ライラック」
作中でヘートヴィヒは、綺麗な花や木に囲まれた暮らしを人一倍気に入っており、将来的には農業をやりたい、という夢を持っています。
この自然を大切にするヘートヴィヒの嗜好は、「血と土」という理念を重ね合わせると、彼女の好みであるとともに、国としての農本主義的活動の一環を担っていることがわかります。
青々とした緑や、色とりどりの花が咲く、美しい自然に囲まれた環境でのヘス一家の生活は、まさにナチスが推進していた「血と土」に基づく生き方であり、結果的にヘス家は、この考え方における素晴らしいモデルとなっています。
また、ルドルフ・ヘスが、SS隊員に対して「兵舎横のライラックを摘み取るときは茂みを傷つけないように」「木が血を流すような乱暴なやり方をした者は罰せられる」と注意を促すシーンがありました。
この描写からは、国家が掲げる農本主義的な“自然を大切にする思想”が、収容所の植栽にまで適用されるほど、隅々にまで徹底して浸透していたことがうかがえます。
収容所内では、大量のユダヤ人が殺害されている一方、ライラックという植物が「人間(ユダヤ人)以上に大切に扱われている」という異様な価値観を、対比的に表現しており、彼らの関心は、同じ種族であるはずの人間ではなく、植物に向いているという事実にゾッとしました。
(ライラック=「収容されているユダヤ人少女」を指す隠語だという解釈もありましたが、実際アウシュヴィッツの周りにはライラックが咲いていたことを考えると、言葉通り「ライラックを傷つけないよう注意した」という受け取り方が個人的にはしっくりきました)
私たちはヘス一家の無関心を批判できるのか
さて、ここまで散々ヘス家、おもにヘートヴィヒの感覚を批判的に書いてきましたが、外側から観ている私たち自身が持っている感覚は、果たして”彼らとは違う”と言い切れるでしょうか。
ここが本作の肝であり、監督の意図だと思われます。
よくないと分かっていたはずなのに、無意識に目を背けているうちに気にならなくなってしまったこと。
おかしいと感じていたのに「そういうものだ」と自分へ思い込ませるうちに、本当になにも感じなくなってしまったこと。
ヘス家が壁の向こう側を気にせず生活していた理由ともなる性質が、私たちにも存在しているのです。
最初は「アウシュヴィッツの横で暮らす家族を観察する」ような気持ちで、彼らを完全に切り離して観ていましたが、だんだん「アウシュヴィッツの横で暮らす家族と私たちの違いはなにか」を考えながら観ている自分がいました。
自分がヘス一家と同じ立場に立ったとき、ただ普通に生活をしていただけの彼らを堂々と怒れるような、誰にも恥じない後悔をしない行動を取ることが私たちにできるでしょうか。
私は正直、自信を持って「できる」とは言い切れません。
人間に備わった”無関心”というものの恐ろしさが、いつか自分たちの身を滅ぼしかねないことを、私たちは忘れてはいけない、と気づかせられた作品でした。
まとめ
今回は「関心領域 The Zone of Interest」をご紹介しました。
いろんな意味で心にダメージを負う映画でしたが、ホロコーストについて学ぶとてもいいきっかけになり、観てよかったなと思います。
ただ、この映画の全容を捉えるには、鑑賞後の情報収集は絶対だと感じました。
当時のヘス家を忠実に再現した映像の中では、ところどころなにを意図しているのかがわからないシーンがあり、初見で完全に理解をするのは難しかったです。
一つ一つのシーンに深い意味が込められているので、気になったところは詳しい解説をされている方の記事を探してみることをおすすめします。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
それでは!
▼参考
ホロコースト百科事典|アーリア
アウシュビッツ収容所の恐怖を音で表現!映画『関心領域』特別映像
絶賛上映中『関心領域』特別映像_俳優が明かす撮影の裏側
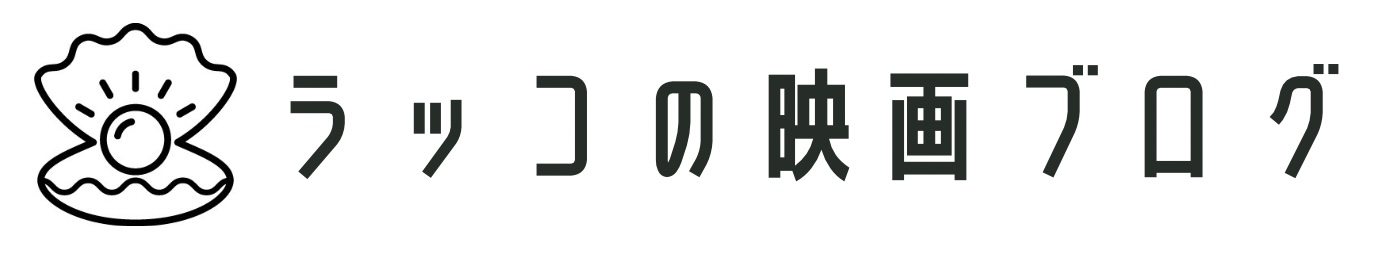
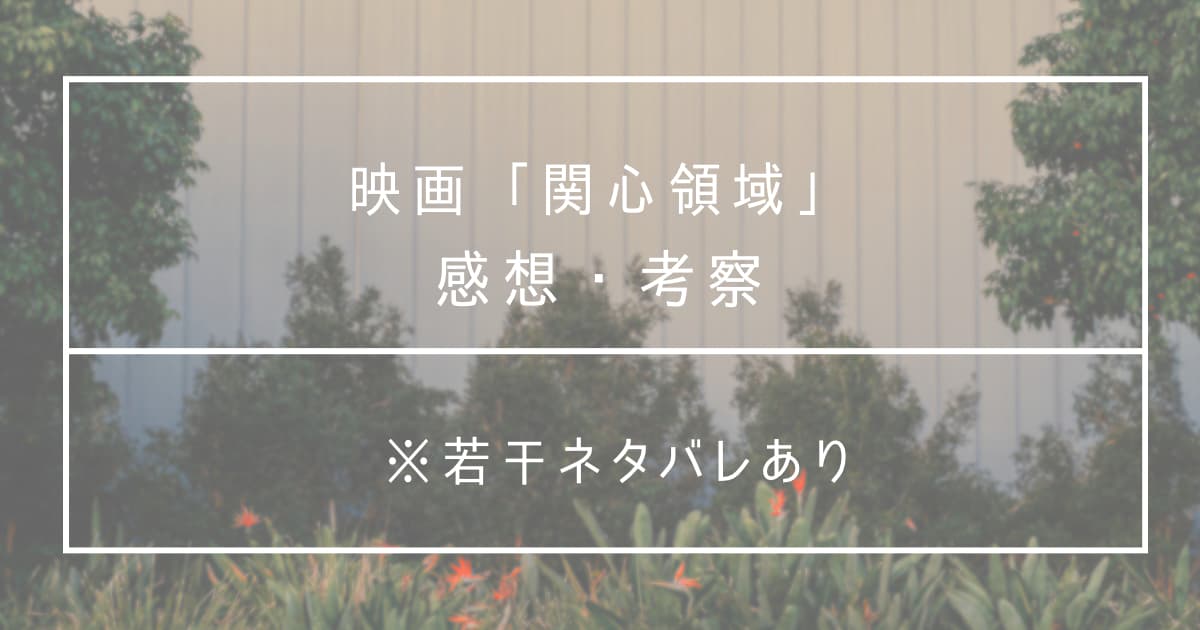

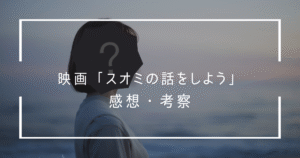

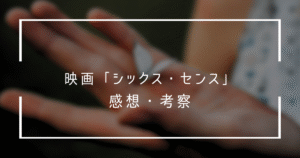
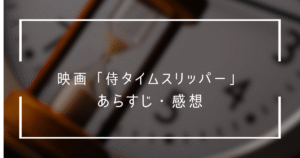
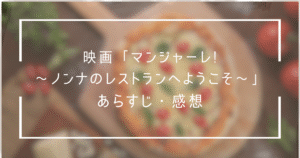
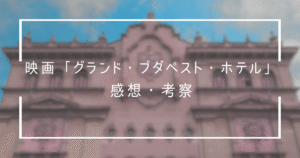
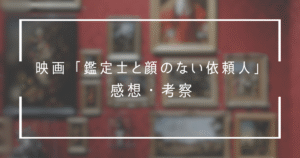
コメント