こんにちは、ラッコです。
Netflixにて配信中の「幸せの列車に乗せられた少年(Il treno dei bambini)」を鑑賞しました!(2025年1月時点)
戦後のイタリアで実際に行われていた「子ども列車」という取り組みを題材にした映画で、貧富の格差や親子の愛を描いた物語。
原作はヴィオラ・アルドーネの同名小説で、イタリアでは30万部を売り上げるベストセラーとなっています。
俳優陣の表現力が素晴らしく、心にグッと染みる良作映画でした。早速紹介していきます。
 らっこ
らっこ原題の「il treno dei bambini」は直訳すると「子どもたちの列車」だそうです
・親子の関係を題材にした映画を観たい方
・戦後イタリアの様子に興味がある
作品概要
| 題名 | 幸せの列車に乗せられた少年(原題:Il treno dei bambini) |
| 公開年 | 2024年 |
| 監督 | クリスチナ・コメンチーニ |
| キャスト | クリスチャン・セルヴォーネ(主人公の少年/アメリーゴ) –ステファノ・アコルシ(大人になったアメリーゴ) セレナ・ロッシ(アメリーゴの母/アントニエッタ) バルバラ・ロンキ(北部の受け入れ先の女性/デルナ) |
| 公式サイト | 映画『幸せの列車に乗せられた少年』Netflix公式サイト |
あらすじ
第二次世界大戦直後のイタリア南部・ナポリで、母/アントニエッタと2人で暮らしている少年/アメリーゴ・スペランツァ。
貧しく学校に通うことができず、8歳ながらに家計を助けるため仕事をする日々が続く。
当時イタリアでは、戦後の復興が遅れていた南部の貧しい地域の子どもたちを、冬の寒い間だけ北部の一般家庭へ預ける「子ども列車」という活動が行われていた。
この活動に対しナポリでは賛否があり、街中で反対の声を上げる人々がいる中で、母/アントニエッタは息子/アメリーゴを列車に乗せる決断をする。
アメリーゴを送り出した母にはどのような想いがったのか———————
感想・考察
これから鑑賞される方へ(ネタバレなし)
タイトルを見て心温まるお話かと思い軽い気持ちで見始めましたが、いざ鑑賞し終えるとかなり考えさせられるお話でした。
子供列車という取り組み
まずは「子ども列車」という取り組みについて。
イタリア南部の貧困家庭の子どもを北部の裕福な家庭が一時的に引き受ける、短期的な里親制度のような取り組みで、劇中では共産主義の女性が中心となって、列車で子どもたちを北部へと連れて行きます。
この活動は戦後のイタリアで実際に行われていたそうなのですが、お恥ずかしいことにこの映画を観るまでは存在すら知りませんでした。
子供を列車に乗せる決断の重たさ
映画の中では、「子ども列車」という活動に反対する人たちもいて、「本当は敵国であったソ連に連れていかれる」「子どもは手足を切り落とされて窯に入れられる」といった真偽の分からない噂も飛び交います。
たしかに、お金などなんの対価もなしに貧困地域の子どもたちを助けてくれるなんて、そんな都合のいい話を信じられない気持ちはすごく分かります。
もし本当に北部の地域へ送り出すにしても、温かい家庭に受け入れてもらえるのか、どんな人たちと過ごすのか、北部での生活の豊かさに触れることで南部の生活に嫌気が差し、もう戻ってこないのではないか・・・といったさまざまな不安がある中で、親たちは子どものためを想い、北部へ送り出します。
主人公アメリーゴの母であるアントニエッタも、悩んだ末に息子を列車に乗せる決断をします。
そばにいる唯一の家族を、たとえ一時的とはいえ手放すという選択は、これほど苦渋という言葉が合う場面はないのではないかというくらい、重く辛いものだったと思います。
注目すべきは少年の演技
この映画を観るにあたって特に注目してもらいたいのは、登場人物たちの演技力(特に表情)です。
主人公のアメリーゴや母であるアントニエッタをはじめとして、出てくる人たちみんな非常に演技が上手く、まるで当時のイタリアの映像をそのまま観ているかのようでした。
セリフがない場面でも、表情だけでその人物が何を考えているかが観ている側に伝わるすごさ・・・。
イタリアの映画って今まであまり観たことがなかったのですが、子役でさえそれができてしまうというレベルの高さに驚きました。
「愛」ってなんだろう、「幸せ」ってなんだろう、と深く考えさせられる映画でした。



イタリアの歴史を知らなくても楽しめたけど、知っていたらもっと理解が深まったかも!
ここからネタバレあり ※未鑑賞の方は注意
あらすじを読んで、少年が大人になっていく過程が細かく描かれていくんだと思っていましたが、意外と映画自体が短かったです。
その分、物語において重要なことや伝えたいことが綺麗にまとめられていて、非常に観やすかったなと思います。
というわけで、まずは個人的に注目してほしいポイントを2つ紹介していきます。
注目ポイント「貧富の差」
まず注目させられるのは「貧富の格差」です。
主人公・アメリーゴは貧乏な家庭で生まれ育ち、服はボロボロで靴を買うお金もなく、学校は通わないのが当たり前で字も読めません。
職業を自由に選ぶことはできず、家計を助けるために早くから働く子どもたちもいます。
一方北部の比較的裕福な家庭では、自分の体型に合った服、もちろん靴や寒さを凌ぐコートまで揃っていて、食事もチーズはハムなど貧しい地域では食べられないような美味しいものが毎日食卓に並びます。
子どもたちは学校へ通い教育を受けるのが当たり前で、本人が望めば楽器を習うこともできます。
北部へ行ったアメリーゴは、デルナという独身女性に引き取られ、近所に住むデルナの兄の家族たちと生活を共にします。
暖かい服や食べ物を与えられ、学校に通い、家畜の世話を手伝い、ときには楽器を弾くなど、南部にいたときから大きく生活が変わりました。
汚れた服を着て裸足で過ごしていた南部での生活との違いを見て、この時代のイタリアでは「どこに生まれるかで子どもの将来は大きく左右される」のだということを感じました。
アメリーゴは北部で生活をしていくうちに、不器用ながら丁寧に接してくれるデルナや、アメリーゴに音楽の才能を見出しバイオリンを教えてくれるデルナの兄、年が近く喧嘩をしながらもお互いを助け合う兄弟的な関係となったデルナの甥っ子などたくさんの人の愛情に囲まれて、血はつながっていなくともまるで本当の家族のようになっていきます。
注目ポイント「親子の関係」
母アントニエッタはアメリーゴと接するとき、笑顔がなくすごくぶっきらぼうに見えます。
アメリーゴのことを大切に思っているのは見て取れますが、自分の気持ちを言葉にするのが苦手で、息子のことを「神からの罰」と言ってしまうことも。
お世辞にも「優しいお母さん」とは言えず息子に対していつもそっけない態度をとっています。
はっきりとは描かれていないので分かりませんが、アントニエッタがアメリーゴを列車に乗せた理由として「自分のところにいてほしいけど、北部の裕福な地域で生活した方がアメリーゴは幸せになれる」と考えたというのは少なからずあると思います。
夫がアメリカに行ってしまいアメリーゴと二人暮らしのアントニエッタにとって、アメリーゴはそばにいる唯一の大切な家族です。
そんな大切な息子を一時的とはいえ手放すことを選択したのは、不器用なアントニエッタなりの最上の愛だったのだろうなと思います。
以上の「貧富の差」「親子の関係」をベースに物語は進んでいきます。
続いて、その中でも印象に残ったシーンをご紹介します。
アメリーゴの自我の芽生え
北部での生活を終えたアメリーゴが南部へ帰ってきた際、北部でもらったお土産のモルタデッラ(というハム)入りのサンドイッチや自分の名前入りのバイオリンを見せる姿を目にして、アントニエッタはイライラした様子で強く当たりはじめます。
おまけにアメリーゴが大切に持って帰ってきたバイオリンを「遊んでいる時間はない」「今は必要ない」とベッドの下にしまってしまいます。



冒頭でアメリーゴはバイオリニストになっていたので、この時点で「もしかして北部に戻るのか・・・?」と勘づいてしまいました
息子の幸せを願っていたはずなのに、貧乏な自分では到底経験させてあげられないこと北部でたくさん享受してきたアメリーゴの姿を見て嫉妬や悲しみの感情を抱いてしまったアントニエッタ。
「こんなことになるなら列車に乗せなければ良かった」とすら思っているように見えて、ここでも母の不器用で未熟な部分が出てしまいます。
アメリーゴからしたら、母の決断で列車に乗せられてただ帰ってきただけなのに、そんなふうに言われたらムカついて当然ですよね。
その後、なんとアントニエッタはバイオリンを質に入れてしまいます。
アメリーゴの服や食べ物を買うためだと言っていますが、北部での暮らしを忘れさせたい気持ちが大きかったように思います。
北部から来ていた手紙や荷物を受け取らず、アメリーゴには「届いていない」と嘘をついていたのも、このまま北部との繋がりが続くことでアメリーゴが北部へ戻りたくなってしまうのではないかと不安になったのでしょう・・・。
しかし、北部との関係を断ち切ろうとするアントニエッタの行動が引き金となり、アメリーゴは南部の家を飛び出し北部のデルナたちのもとで暮らしていくことを選びます。
今まで母の言う通り生きてきたアメリーゴでしたが、北部での生活を経て、自分がどうしたいかを考えた上で自分の人生を選択したのです。
素直じゃない、愛し方がわからない母の気持ちがアメリーゴには伝わらず、逆に「自分は北部で暮らしていた方が幸せだ」とアメリーゴに思わせてしまったのは、もちろん自業自得とはいえアントニエッタはものすごくショックを受けたのではないでしょうか。
ただ、このアントニエッタの身勝手な態度は「貧富の差」という部分も関連しているのではないかとわたしは感じました。
彼女自身がもともと不器用で素直になれない性格だからというのもあると思いますが、個人的には、お金がなく生活をするのに必死で心がいっぱいいっぱいであるが故にアメリーゴに強く当たってしまう部分もあるのではないか、と思っています。
もしこの二人のお家にもう少しお金があれば、アントニエッタには多少なりとも心のゆとりができて、北部から帰ってきたアメリーゴにも嫉妬することなく優しく接することができていたんじゃないか、そうであれば二人は離れ離れになることはなかったんじゃないかとつい考えてしまいました。
買い戻されたバイオリン
アントニエッタの訃報を受け、大人になったアメリーゴが南部の家へ飛び出して以来初めて帰ったシーン。
ベッドの下からはなんと、かつて質に入れられた自分のバイオリンが発見されます。
この買い戻されたバイオリンには、アントニエッタの「いつかアメリーゴが戻ってくるかもしれない」という気持ちが詰まっている気がして涙が出そうになりました。
アメリーゴにバイオリンを返して仲直りする未来を描いていたのだろうと思うと余計辛くなります。
本当は戻ってきてほしくて仕方がなかったはずなのに、それでも北部へ迎えに行かなかったのは、アメリーゴの選択を尊重した、母からの最後の愛だったのです。このバイオリンを通して、アメリーゴは大人になってようやく母からとても愛されていたことに気がつきました。
冒頭のりんごと革靴
映画の冒頭の、バイオリニストになったアメリーゴがコンサート会場の控室にいる場面では、籠に盛られたりんご・衣装であろう立派な三足の革靴が置かれています。
冒頭も冒頭なので最初は何も思いませんでしたが、後から見返すと、「列車へ乗る直前に唯一母が持たせれくれた一玉のりんご」や、「貧しくて履くことができなかった靴」が大人になっている今ではごく当たり前に手に入るようになっている、ということを表しているのだと気がつき、すごく凝っているなと思いました。
まとめ
今回は「Il treno dei bambini/幸せの列車に乗せられた少年」をご紹介しました。
原作がベストセラー小説ということもあって、ストーリーや展開の土台がしっかりしていて、無駄な要素のない綺麗にまとめられた映画だったなと思います。
「貧富の差」「親子の愛」など注目すべきポイントも分かりやすく、解釈の余地を残してくれる部分もあって映画の構成も非常に良かったです。
実際、アメリーゴやアントニエッタがとった行動の意味や、登場した子どもたちにとっての幸せとはなんだったのか、などわたし自身すごく考えさせられました。
気になった方はぜひ観てみてください!
それでは。
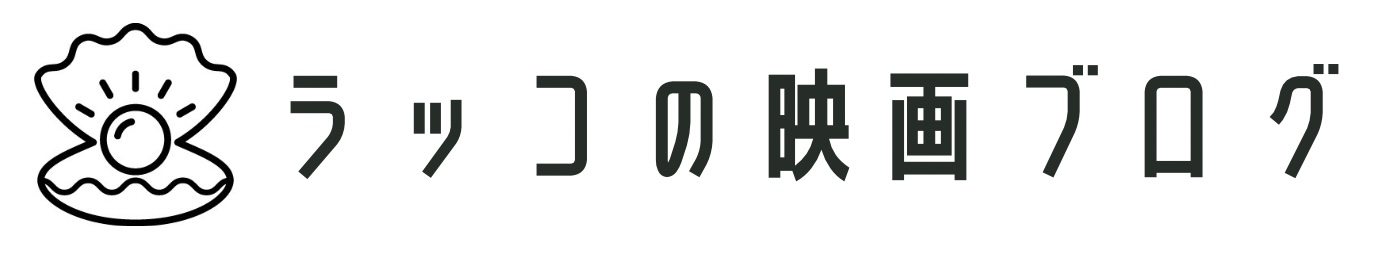
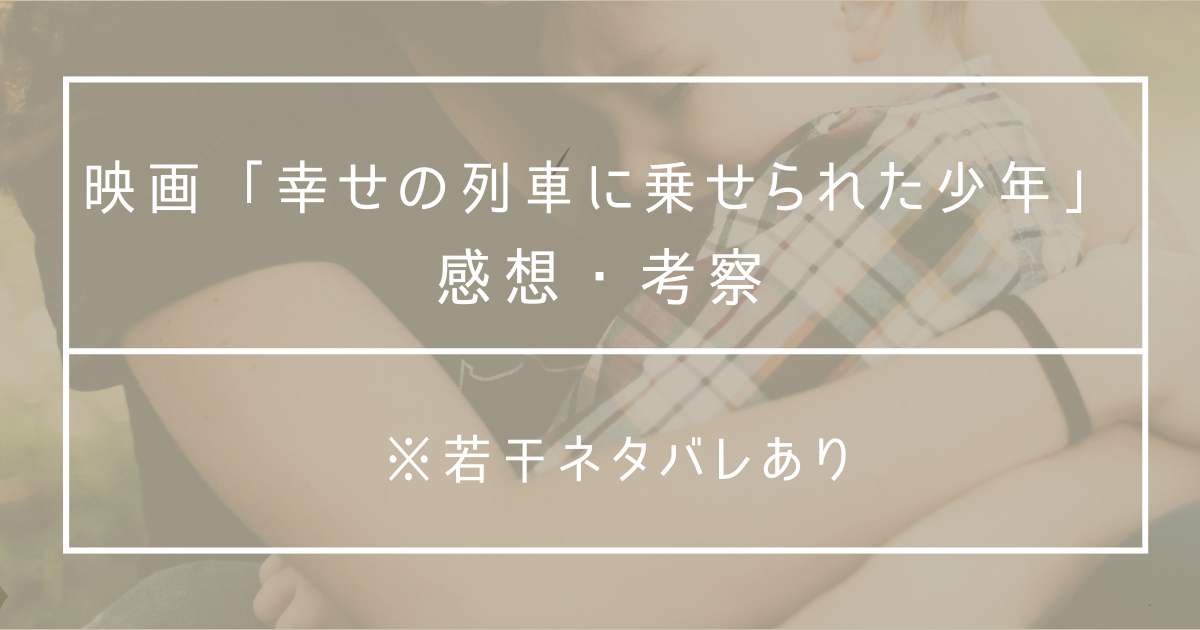

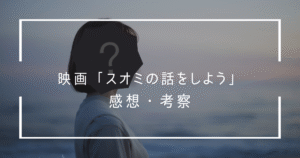

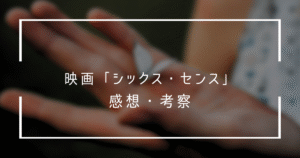
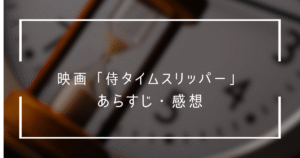
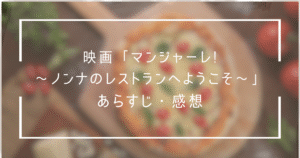
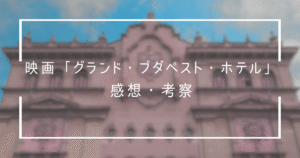
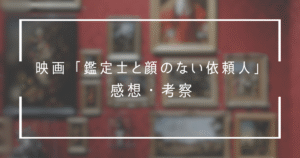
コメント