こんにちは、ラッコです。
今回はAmazonPrimeで配信中の映画「シックス・センス」を鑑賞しました!
1999年に公開されたアメリカのホラーミステリー作品。
小学生のころに観たワンシーンがあまりに怖くて、「超絶恐怖ホラー映画」だと思い込み、ずっと避けてきた作品でした。
でも、大人になった今、改めて最初から最後まで観てみると、いい意味でそのイメージが覆されました・・・
20年以上経った今でもまったく色褪せない、言わずと知れた名作です。
作品概要
| 題名 | シックス・センス(原題:The Sixth Sense) |
| 公開年 | 1999年(日本公開は2001年) |
| 監督 | M・ナイト・シャマラン |
| キャスト | ブルース・ウィリス(マルコム・クロウ) ハーレイ・ジョエル・オスメント(コール・シアー) トニ・コレット(リン・シアー) オリヴィア・ウィリアムズ(アンナ・クロウ) ドニー・ウォルバーグ(ヴィンセント・グレイ) |
| 公式サイト | なし |
あらすじ
数々の子どもたちを救ってきた児童心理学者・マルコム(ブルース・ウィリス)。
かつて担当していた少年患者ヴィンセントの治療に失敗し、彼に自宅を襲撃されてしまう。
命は取り留めたものの、その出来事はマルコムの心に深い傷を残した。
そんな彼が新たに担当することになったのは、周囲になじめず孤立している8歳の少年・コール(ハーレイ・ジョエル・オスメント)。
最初は心を閉ざしていたコールだったが、マルコムの誠実な態度に少しずつ打ち解けていく。
そしてついに、彼はマルコムに「死んだ人が見える」ことを打ち明ける。
二人の絆が深まる中で、やがて“ある真実”が明らかになっていく——。
感想・考察
鑑賞前の方は今すぐ閉じて!絶対にネタバレ厳禁
まず、これから鑑賞予定の方は、ぜひこのまま何も見ずに、とりあえず本編を鑑賞されることをおすすめします。
ネットで少し検索しただけでも、うっかり大事な情報を拾ってしまうことがありますので・・・
ここで一旦ページを閉じて、先に映画を観た方がより楽しめること間違いなしです。
 らっこ
らっこここからは映画の内容にも触れていくよ
本作のラストを知ることなくここまで生きてこられたというのは、とても幸運なことです。
名作なだけあって、感想や考察を目にする機会も多いので、もし本作について何も知らない方がいたら、それだけで人生得していると言っても過言ではありません!
かくいうわたしは、かつてワンシーンだけ観たことがあるのですが、それが怖すぎて、今まで全力で本作を避けてきました。
そのおかげで、今回”ほぼ何も知らない状態”で鑑賞するという、奇跡的な体験ができたことのありがたさたるや。
「ラストに何かが起こるらしい」とだけ知っている方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん知っていても楽しめるとは思うのですが、本作の魅力を最大限享受しようと思ったら、やはりまっさらな状態で観るのがいいかなと思います。
絶妙なホラー演出
小学生の頃のわたしはワンシーンだけで相当びびっていましたが、大人になった今あらためて観てみると、「ホラー」とはいえミステリー要素が強く、怖がらせる演出は思ったより控えめ。
ホラー映画としては、軽めの部類だと感じました。
派手な驚かせ方ではなく、心理的な怖さでじわじわとドキドキさせられる感じ。
コールには“死者が見える”という特殊な力がありますが、「次のシーンで幽霊出てきそう…」というのが音と演出でなんとなく察せられて、構えておけるのがありがたいところです。
コールが恐怖におびえている姿を見るうちに、自然とこちらも息をのんでしまう——そんな共鳴する怖さがありました。
あまりに怖いと、鑑賞後にストーリーの余韻に浸る余裕がなく、ただ怖かったという感情だけが残ってしまいますが、その点で言うと本作は、ホラー演出がとても絶妙でした。
怖さの程度がわたしには合っていて、物語の深さをしっかり味わうことができました。
コールを演じたハーレイ・ジョエル・オスメントの圧巻の演技
そして、その怖さをより引き立てていたのが、コールを演じたハーレイ・ジョエル・オスメントの演技です。
幽霊が現れたときの息遣いや怯えた表情、マルコムに意を決して秘密を打ち明けるときの縋るような目つき。
どれもリアルで、11歳とは思えないほどの説得力があります。
恐怖におびえるコールの演技がとても自然で、「現場に本当に幽霊がいたの?」と思ってしまうほどリアルです。
そのおかげで、演技を変に意識せずに物語に没入できます。
無駄のない完成度、これぞ名作
ストーリーには無駄がなく、とてもきれいにまとめられています。
ホラーとしてもミステリーとしても一級品で、伏線の散りばめ方もとても巧妙です。
その伏線たちが、ラストで一気に意味を持つ構造は、何度観ても感心させられます。
しかも、わざとらしくなく自然に配置されているので、初見でラストの展開を正確に予想できる人はほとんどいないのではないかと思います。
設定、ストーリー、映像表現、すべてがぴたりとはまっていて、文句なしに素晴らしい作品です。
名作と呼ばれている理由が、否が応でもわかります。
あのまま小学生時代の“怖い”というイメージに囚われて観ていなかったら、とても後悔していたと思います。
当時の恐怖感も払拭でき、何より素晴らしい映画に出会えたことがうれしい!
ホラーが苦手だけれど挑戦してみたい!という方にも、自信を持っておすすめできる作品です。
ここからネタバレあり ※未鑑賞の方は注意
静かに明かされる真実
コールを救うために、彼に真剣に向き合い続けてきたマルコム。
マルコムとのやり取りの中で、コールは自分の前に現れる幽霊と向き合うことを決め、次第に日常的に感じていた恐怖心から解放されていきます。
しかしその矢先、悲しくも受け入れざるを得ない事実が突きつけられます。
なんと——マルコムはすでに亡くなっていたのです。
まったく予想もしなかったこの結末に、思わず息を呑みました。
せっかくコールと心を通わせ、次は妻・アンナとの関係を修復していくぞ、という段階だったのに・・・
そもそも亡くなっていた、という未来のない展開があまりにも切ない。
冒頭のシーンで、かつての患者ヴィンセントがマルコムの自宅に侵入し、彼を銃撃して自らも命を絶つ場面がありました。
映画では一命を取り留めたように見えましたが、実際にはマルコムはその時すでに命を落としていたのです。
見事な伏線!何度も見返したくなる理由
こうなると、これまでのマルコムの妻・アンナの行動は、まったく違った見え方になります。
マルコムに冷たくなり、挙句の果てには別の男性に心を向けかけていたアンナ。
しかしその行動は、愛情の欠如ではなく、「マルコムを失った悲しみから立ち直れない苦しみ」の表れだったのです。
マルコムの視点で“すれ違い”のように描かれ、ラストで真実が明かされる構成は本当に巧みで、まんまと騙されました。
むしろ気持ちよく騙されたというか、純粋に物語に入り込めた感覚がありました。
この真相を知ったうえで改めて本作を観ると、マルコムがアンナの寝顔を見つめるシーンで、彼女の手に握られていたティッシュは、おそらくマルコムを想って流した涙を拭いたものだったのだと気づきます。
また、結婚記念日の食事の場面で、遅刻したマルコムに対してアンナが怒っているように見えたのも、実は“亡き夫を忘れられずにいる”彼女の悲しみの裏返し。
不仲どころか、深い愛情をずっと胸に抱いていたのです。
こうして振り返ると、マルコムの死は物語の随所にさりげなく伏線として描かれていました。
そのひとつが、彼が地下の書斎に入る際、“ドアを開ける描写”が一度もないこと。
実際にはドアには鍵がかけられ、重たい本棚で塞がれていたにもかかわらず、マルコムは何の違和感もなく部屋に出入りしていました。
「幽霊には見たいものしか見えない」——つまり、マルコムにはその障害が見えていなかったのです。
ほかにも、コール以外の誰とも会話しないなど、観客が気づかぬほど静かな違和感が積み重ねられていました。
そしてラスト、アンナの手からマルコムの指輪が落ちることで、彼はようやく“自分の死”に気づきます。
マルコムが自分の真実に気づくきっかけとして、これほど美しく象徴的な演出はないと思います。
その後、書斎のドアに目を向け、彼はようやくドアを塞ぐ本棚の存在に気がつくのです。
静かで、胸の奥をじんわり締めつけるような名シーンでした。
「白い息」と「赤色」が告げる異変
本作では、幽霊が現れるときに描かれる特徴が二つあります。
ひとつ目は「白い息」。
コールによると、幽霊が現れるとき、人は寒気を感じ、お腹の奥がぎゅっと締めつけられるような感覚に襲われるのだそう。
実際、コールの前に幽霊が現れるとき、彼の口からは白い息が漏れています。
この演出がとくに印象的なのが、ラストシーン。
アンナがマルコムの指輪を落としたことで、彼は自分の指に指輪がないことに気づきます。
その瞬間、マルコムの脳裏にはコールの言葉——
「幽霊は自分が死んだと思っていない」「彼らはしょっちゅう現れる」「彼らには見たいものしか見えない」
——がフラッシュバックします。
そしてアンナを見ると、彼女の口からは白い息が・・・
この一連の流れで、マルコムはついに自分が“もうこの世の人ではない”ことを悟るのです。
白い息という演出は、観客にとっては幽霊出現の前兆を示すサインであり、マルコムにとっては“真実に気づくための手がかり”として機能していました。
恐怖演出にとどまらず、物語全体を象徴する巧みな仕掛けだと思います。
そして二つ目の特徴が「赤色」。
本作を象徴する色彩表現のひとつです。
教会の扉、コールの隠れ家のテント、マルコムの書斎のドアノブ、赤い風船——
どれも“死者との接点”や“死の世界の象徴”として配置されています。
中でも印象的なのは、少女キラの母親が葬式で着ていた赤いドレス。
キラを死に追いやった本人であり、もっとも“死”に近い場所にいた存在だからこそ、彼女は赤をまとっていたのでしょう。
監督であるM・ナイト・シャマランは、本作以外にも色彩に意味を持たせる演出を取り入れているようで、こうしたセンスが物語に奥行きを持たせているのだと感じました。
親子の絆には、思わず涙する
コールの家は、父親が出て行ってしまってから、母親との二人暮らし。
母親はとても息子思いで、コールと接するシーンの端々から、彼を人一倍大切に想っていることが伝わってきます。
しかしコールは、“幽霊が見える”という事実を母親に打ち明けることができず、マルコムに出会うまではずっと一人で抱え続けていました。
作中では、幽霊が起こした出来事をコールのせいにされてしまう場面もあります。
母親に疑われても、「幽霊が見える」と言っても信じてもらえない・・・と言う思いから、真実を言えずにいるコールの苦しさは、胸に迫るものがあります。
一方で、母親にも“息子のことを理解したいのに、心を閉ざされてしまう”という葛藤があり、無理に聞き出そうとしない優しさが切なく映ります。
どちらの気持ちも分かるからこそ、この二人の関係性は、観ていてもどかしかったです。
そんな二人の距離が一気に縮まるのは、やはり“コールが幽霊が見えることを母に打ち明けるシーン”。
母子の絆が深まる瞬間であり、作品全体に温もりをもたらす名場面です。
コールの告白に、最初は信じられない様子を見せる母。
しかし、コールは“亡くなった祖母(母の母)が自分のもとへ来ていること”、そして“母に伝えたい言葉がある”と語ります。
祖母と母が喧嘩をした日のこと。
母のダンス発表会を、母は気づいていなかったけれど祖母はちゃんと見ていた——。
そして、祖母の亡き後に、お墓の前で母がつぶやいた質問への答え。
「毎日よ。」
質問の内容を知らないコールが「何を聞いたの?」と尋ねると、
母は静かに「私のことを誇りに思っていた?」と聞いたのよ、と答えます。
そんな、コールが知るはずのない“母と祖母だけの思い出”を語る彼を見て、母は涙ながらにコールを抱きしめます。
その涙には、すぐに息子を信じてあげられなかった悔しさ、
大切なことを打ち明けてくれた嬉しさ、
そして“亡き母は自分を愛してくれていたのだ”という安堵が入り混じっているように感じました。
家族の絆が確かに結ばれ、コールの心に長く重くのしかかっていたものがそっと解き放たれたような、静かで温かく、胸に残る名シーンでした。
恐怖を越えて生まれた“信頼”
ラストを知ったうえで気になるのは、コールはマルコムが亡くなっていたことに気づいていたのかどうか。
結論から言うと、わたしは“気づいていた”と思います。
コールが学校から帰宅した際、母の座る椅子の前にマルコムが座っているシーン。
そのときのコールの表情をよく見ると、マルコムを目にした瞬間に一瞬硬直し、驚きと怯えのような表情を浮かべています。
しかし、会話を交わすうちに彼が自分を傷つける存在ではないとわかり、次第に自然に話せるようになっていく。
最初は警戒しながらも、やがて心を開いていく過程がとても丁寧に描かれています。
この一言が、マルコムが真実に気づくきっかけとなり、同時に彼を“救う”きっかけにもなります。
そして迎える、二人の別れのシーン。
成長したコールを見て、マルコムは「もう自分は彼には必要ない」と悟ります。
「もう会えないの?」というコールの問いに、マルコムは「僕らは話し合ってきた。君は母親とも素直に話すべきだ」とだけ答えます。
マルコムにとってそれは、“治療が終わったから去る”という意味。
しかし、マルコムの死を知っているコールにとっては違います。
マルコムが妻と向き合うということは、自らの死を受け入れるということ。
つまり、彼は成仏し、もう二度と会えない。
そう考えると、その後の「また会えるふりをして」というコールの台詞が、子どもらしい優しさと切なさを帯びて、胸に迫ります。
コールの前に現れる死者たちは皆、救いを求めています。
そしてマルコムもまた、かつての過ちを悔い、愛する妻ともう一度心を通わせたいと願った“ひとりの迷える魂”でした。
コールはマルコムがいなくなってしまうことをわかりつつも、彼を導き、そして送り出したのです。
お互いがお互いを救い合ったという特別な関係であることが、観客に伝わったときには、もうすでに二人は会えなくなっている——。
ホラー映画とは思えないほど、切なくて温かいラストには思わず涙してしまいました。
まとめ
今回はAmazonPrimeで配信中の映画「シックス・センス」を鑑賞しました!
ホラー映画のイメージをいい意味で覆してくれる、とても素晴らしい作品です。
定期的に見返したくなる、大切な一本になりました。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
それでは。
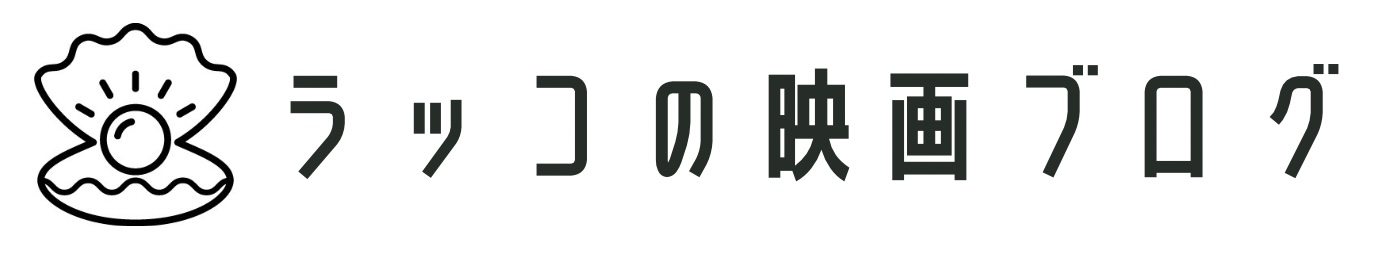
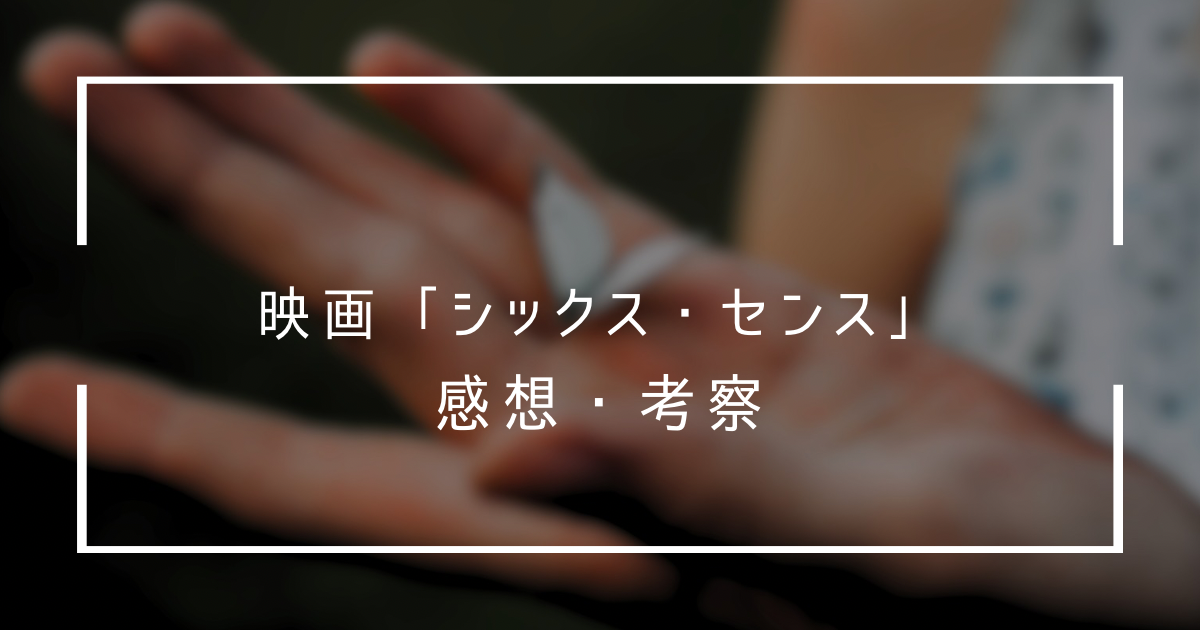

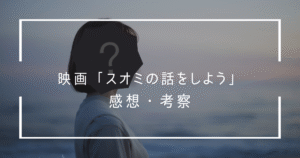

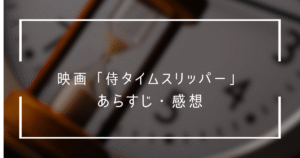
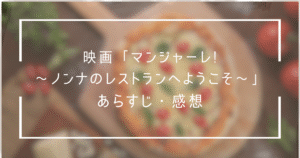
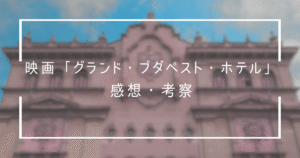
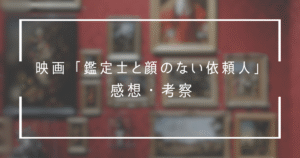
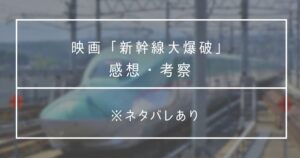
コメント