こんにちは、ラッコです。
今回はAmazon Primeで映画「グランド・ブダペスト・ホテル」を鑑賞しました!
言わずと知れたウェス・アンダーソンが監督を務めた本作。
舞台は、カラフルで、おもちゃの世界に迷い込んだかのようなホテル。
その中で、美しくも残酷で、どこか心温まる物語が繰り広げられていきます。
早速ご紹介していきます!
・アートのような美しい背景を楽しみたい
・テンポのいい作品が好き
・コメディ映画が観たい
作品概要
| 題名 | グランド・ブダペスト・ホテル(原題:The Grand Budapest Hotel) |
| 公開年 | 2014年 |
| 監督 | ウェス・アンダーソン |
| キャスト | レイフ・ファインズ(ムッシュ・グスタヴ・H ) トニー・レヴォロリ(ゼロ) –F・マーリー・エイブラハム(1968年のゼロ) トム・ウィルキンソン(作家) シアーシャ・ローナン(アガサ) ティルダ・スウィンソン(マダムD) |
| 公式サイト | なし |
あらすじ
舞台は1932年、架空の国ズブロフカ共和国。
超高級ホテル『グランド・ブダペスト・ホテル』には、伝説のコンシェルジュ、グスタヴ・Hがいました。
おもてなしの達人である彼のもとで、ホテルに憧れていた青年ゼロがベルボーイとして働き始めます。
しかし物語は、常連客の富豪であるマダムDの死によって大きく動き出します。
マダムDの遺言によって貴重な絵画を相続することになったグスタヴ。
よそものに財産を奪われたと憤ったマダムDの息子ドミトリーは、グスタヴをマダムD殺害の容疑者に仕立て上げ、絵画を取り戻そうと動き出します。
こうしてグスタヴとゼロの、絵画を巡る波乱の逃走劇が幕を開けます。
感想・考察
これから鑑賞される方へ(ネタバレなし)
これぞウェス・アンダーソン!めくるめく映像美
ウェス・アンダーソン作品といえば、まず思い浮かぶのが絵本のように可愛らしい背景。
本作もその魅力にあふれていて、ホテルの外観やエレベーター、大浴場に至るまで、どのシーンを切り取っても、それだけで一枚の作品として成立するほどの美しさがあります。
本作では固定カメラを使ったシーンが多く、さらに多くの場面で左右対称(シンメトリー)が意識されています。
その細部まで計算し尽くされたカメラワークには思わず感心してしまいました。
また、動かない背景の中でキャラクターたちが動き回る様子は、“演じています!”と言わんばかりのコミカルな動きも重なって、まるで人形劇を観ているようです。
他の映画ではあまり見られない独特の演出で、観ていて自然とわくわくさせられました。
撮影はドイツのゲルリッツやドレスデンの街並み・建物で行われたそうです。
監督をはじめとした製作スタッフは、中央ヨーロッパ各地を調査し、空き家になったホテルを片っ端から探したものの、理想の場所は見つからず・・・。
最終的に出会ったのは、廃業していたゲルリッツの百貨店でした。
その内装をホテルとして活用し、装飾はヨーロッパ各地の実在するホテルを参考に徹底的に作り込まれたのだとか。
背景へのこだわりが作品全体に息づいていて、ロケ地探しにも相当な情熱が注がれていたことが伝わってきます。
日本ではなかなか出会えない風景ばかりで、思わず引き込まれてしまいました。
 らっこ
らっこ美しくかわいいシーンがたくさんで、女性ファンが多いというのも納得!
参考:映画「グランド・ブダペスト・ホテル」 メイキング映像
へんてこで愛らしい登場人物
次に注目すべきは、グスタヴやゼロをはじめとした登場人物たち。
グスタヴは、一流のおもてなしを誇るコンシェルジュで、ホテルを常に美しく整える几帳面な性格の持ち主です。
何事も完璧にこなす一方で、マダムD殺害の容疑がかかり警察がやってきた途端、突然背を向け逃げ出したり、感情に任せてゼロに心ない言葉をぶつけてしまったりと、どこか滑稽で人間味あふれる一面も。
それでも根はとても思いやりがあり、ゼロに対してもすぐ謝れる素直さを持っています。
だからこそ周囲から助けられ、慕われる――完璧なのにちょっと抜けている、そのギャップが何とも愛らしいキャラクターでした。



グスタヴを演じるのはレイフ・ファインズ。
『ハリー・ポッター』のヴォルデモート役で知られているけど、実はコミカルな役もぴったり。意外なハマりっぷりにちょっと驚いたよ。
ちなみに『ザ・メニュー』では、レイフ・ファインズが猟奇的なシェフを演じています。
グスタヴとは正反対の姿で、演技の振り幅に驚かされます。こちらもおすすめです!


一方、もうひとりの主要人物であるゼロは、移民としてホテルにやってきた新人ベルボーイ。
彼の目を通して、観客は、かつてグスタヴとゼロの間に起きた出来事を追体験していきます。
なにもかも初心者で、最初は右も左もわからないゼロですが、グスタヴのもとで必死に働き、その健気さから次第に親子のような関係を築き、かわいがられる存在に。
不器用ながらも思い切った行動力を見せ、グスタヴとの絶妙なやり取りもあって、とても愛らしいキャラクターでした。
さらに、マダムDやその息子ドミトリー、そしてホテル近くのお菓子屋メンドルで働く少女アガサなど、クセの強いキャラクターたちが次々と登場。
各登場人物が、物語に華やかさとユーモアを添え、作品全体をより賑やかに彩っていきます。
ただ楽しいだけでは終わらないストーリー
“コメディ映画”と聞くとドタバタ劇を想像しますが、本作はゲラゲラ笑うというより、思わずクスッとするようなシュールさが魅力です。テンポも抜群で、次から次へと事件が起こり、退屈する暇がありません。
また、シンメトリーな構図や直線的なホテルの背景といった、きっちり整った舞台で繰り広げられるちょっとヘンテコな掛け合いは、そのアンバランスさも相まって一層おかしく見えてきます。
ただ、ポップで明るい雰囲気の一方で、物語にはシビアで辛辣な要素も潜んでいます。
コメディとして軽妙に描かれながらも、戦時下であることを感じさせる描写や、遺産相続をめぐるドロドロした争いなど、人間の残酷さが顔をのぞかせる場面も。
そうした光と影のコントラストも、この作品の魅力のひとつだと感じました。
ウェス・アンダーソン映画の奥深さを感じられる一本
本作は、ポップでかわいらしい世界観に包まれながらも、シニカルなユーモアや人間同士のリアルないざこざが絶妙に入り混じった、とてもウェス・アンダーソンらしい作品だと感じました。
登場人物も映像も音楽も、それぞれが強い印象を残していて、ウェス本人を知っているわけではないのに、まるで彼のおもちゃ箱をひっくり返したような作品だなと思います。
軽快なテンポで進む物語は、難しく考えずに楽しめる一方で、観終わった後にはじんわりと余韻が残る──そんな不思議な魅力がありました。
ビジュアルや空気感を味わいたい方にも、めくるめくストーリーを楽しみたい方にもおすすめできる一本です。
(ただ、この独特の空気感が合わないと、人によってはしんどく感じるかもしれません)



吹き替えより字幕で観た方が、より世界観を楽しめるよ!
ここからネタバレあり ※未鑑賞の方は注意
ここからはネタバレも混ぜつつ、作品をさらに深堀していきます!
遊び心あふれる仕掛けに注目
まず、本作は”三重の入れ子構造”で描かれています。
また、時代ごとに縦横比(アスペクト比)を変えて撮影することで、物語の移り変わりがよりはっきりと感じられる工夫もされています。(★)
ひとりの女性が「オールドルッツ墓地」を訪れ、とある作家の墓前で立ち止まります。
手にしていた本には『グランド・ブダペスト・ホテル』の文字。
★ビスタサイズ(1.85:1)
『グランド・ブダペスト・ホテル』の著者である作家が、インタビューを受けるシーンへ。
「この物語は、かつてある人物から聞いた話をもとにしている」と語ります。
★ビスタサイズ(1.85:1)
かつてスランプに陥った作家は、アルプスの麓にある「グランド・ブダペスト・ホテル」でひと夏を過ごしました。
そこで出会ったオーナーのゼロ・ムスタファから、ホテルの過去についての物語を聞くことに。
★シネスコ(2.39:1または2.35:1)
そこから舞台はさらにさかのぼり、『グランド・ブダペスト・ホテル』の初代コンシェルジュであるグスタヴ・Hを主人公とした物語が展開していきます。
★スタンダードサイズ(4:3)
そして物語は、オープニングで登場した女性が、墓地にあるベンチで『グランド・ブダペスト・ホテル』を読んでいるシーンで幕を閉じる──といったおしゃれな構成になっています。
ほかではなかなか見られないユーモアたっぷりのユニークな構造で、とても魅力的ですよね。
ただ、序盤からテンポよく場面が切り替わっていくので、少しでも見逃してしまうと一気に置いていかれます。
ちなみに、ホテルのセット自体も“入れ子構造”になっていたのがおもしろいところ。
1932年のピンク色の全盛期のホテルの上に、1968年の少し廃れたオレンジ色のホテルを重ねて作り、まず68年のシーンを撮影。その後セットを剥がして32年のシーンへ切り替えたそうです。
そして映画の「構造」という点でいえば、同監督の『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』も印象的。まるで映画そのものが一冊の雑誌のように仕立てられていて、こちらも遊び心たっぷりでした。
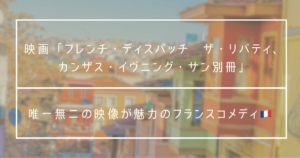
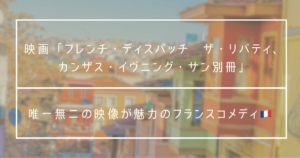
絵画をめぐる物語の終着点
マダムDの遺産である絵画をめぐり、息子ドミトリーから追われていたグスタヴ。
しかし、絵画の裏から「私が殺された時のみ開封のこと」と書かれた新たな遺書が見つかり、そこには「すべてをグスタヴに」と記されていました。
マダムDがこのような遺書を残していたのは、それだけ自分の身を案じていたからでしょう。さらに、親族の名前を一切書かず、ただ一人グスタヴに全財産を譲ったという事実。
それはつまり、親族の誰一人として信用できない状況にあったことを示すと同時に、グスタヴがどれほど信頼されていたかを物語っています。
彼のおもてなしは単なる接客にとどまらず、人々の人生を支える拠り所になっていたのだと感じました。
こうして絵画だけでなく、マダムDの屋敷や工場、さらにはグランド・ブダペスト・ホテルまでも手に入れたグスタヴは、一気に大富豪となります。
その一方で、ゼロもベルボーイから念願のコンシェルジュに昇格。世間では戦争が続く中、彼は変わらずホテルの受付に立ち続けました。
やがてお菓子屋メンドルで働くアガサと結ばれ、二人は小さな結婚式を挙げます。証人を務めたのはもちろんグスタヴ。
理不尽な遺産騒動を経て、この3人がまるで家族のように結びついていったことは、物語の中で唯一心温まる救いの場面ともいえるでしょう。
まさに順風満帆な日々が続くかのように見えました。
けれども――未来のゼロが一人でホテルを訪れていることからもわかるように、彼らの人生はその輝きを永遠に保つことはできなかったのです。
映画が描いた結末と、その余韻
物語の結末は、これまでのテンポそのままに淡々と進みます。
しかし、そこで描かれる出来事は“サラッと流してはならない”重みを持っていました。
まず、アガサについて。
彼女と、ゼロとの間に生まれた息子は、結婚からわずか2年後に流行していたプロイセン風邪により、共に命を落としたと語られます。幸せに満ちていたであろうその時間は一切描かれず、ゼロにとって最愛の家族を亡くした過去は、思い出すことすら辛いものなのだろうと伝わってきました。
そして、グスタヴ。
戦争下で列車に乗っていたゼロとアガサ、そしてグスタヴは、途中で兵士に呼び止められます。
そして移民であるゼロは不法入国者とされ、通行証を破り捨てられて連行されそうになります。
かつて同じことが起きたときは、軍の高官の厚意で幸運にも難を逃れたこともありましたが、今回は違いました。
ゼロを守ろうと抗議したグスタヴは、後に射殺されてしまうのです。
この列車のシーンは、本作で唯一「白黒」のみで描かれています。
この作品において、色彩とストーリーには大きな関係性があり、暗い予兆を示す場面では彩度が落ち、ホテルやメンドルのケーキのように幸福を象徴する場面では鮮やかな色彩が使われてきました。
それを踏まえた上で、“白黒=彩度ゼロ”で描かれた意味を考えたとき、この列車での出来事は、この物語において最も辛く悲しい出来事だったのだと解釈できます。
アガサとグスタヴを失い、一人残されたゼロ。
物語の序盤で、作家が彼を「絶望的なまでに孤独」と表現しましたが、この過去を思うとかなり的を得ていました。
そして印象的なのは、この作品が「死」を過剰に悲劇的に描かない点です。
コメディという作風としての軽やかさを保ちつつ、人は死を抱えながらも前へ進んでいく――そんな姿勢が全編に貫かれているように思いました。
アガサとグスタヴに関しては、ゼロ自身が深く掘り下げることを避けたのかもしれませんが。
グスタヴ亡き後、約束どおりホテルを含む遺産はゼロに引き継がれます。
時代の波に飲み込まれ、大型施設が次々と国に接収されるなか、彼は遺産のほとんどを手放してでも、このグランド・ブダペスト・ホテルだけは守り続ける道を選ぶのでした。
繋がりに気づくともっと面白い!再鑑賞のすすめ
本作は、できれば 2回目の鑑賞をおすすめしたい作品 です。
というのも、1932年から始まるグスタヴ・Hの物語の要素が、1968年のホテルのシーンにさりげなく繋がっているからです。
映画自体は1968年から1932年へと遡る構成になっているため、一度目では見逃してしまう細かな仕掛けが多くあります。
たとえば、グスタヴがマダムDから相続した絵画「少年と林檎」。
グスタヴとゼロが必死に守り抜いたこの絵は、1968年のホテルの受付シーンで、コンシェルジュのムッシュ・ジャンの背後に飾られています。背景の一部として流してしまいそうですが、事情を知ってから改めて観ると「あの絵だ!」と嬉しくなるはず。
また、1968年、ホテルのオーナーであるゼロ・ムスタファは大富豪でありながら、いつもわざわざ狭い風呂なしのシングルルームに泊まっていると語られます。
理由はすぐには明かされませんが、物語が進むにつれ、それが彼がベルボーイ時代に使っていた部屋だったと分かるのです。
わたしは一度目の鑑賞ではすっかり忘れていましたが、二度目に見たときに「あの部屋か!」と気づかされて胸が熱くなりました。
まとめ
今回はAmazon Primeで配信中の「グランド・ブダペスト・ホテル」を鑑賞しました!
色彩の美しさと軽快なテンポの中に、ユーモアと少しの切なさが同居する不思議な魅力を持った作品でした。
観終わったあと、鮮やかな映像とキャラクターたちの余韻が心に残る一本だと思います。
気になった方はぜひみて観てみてください!
それでは。
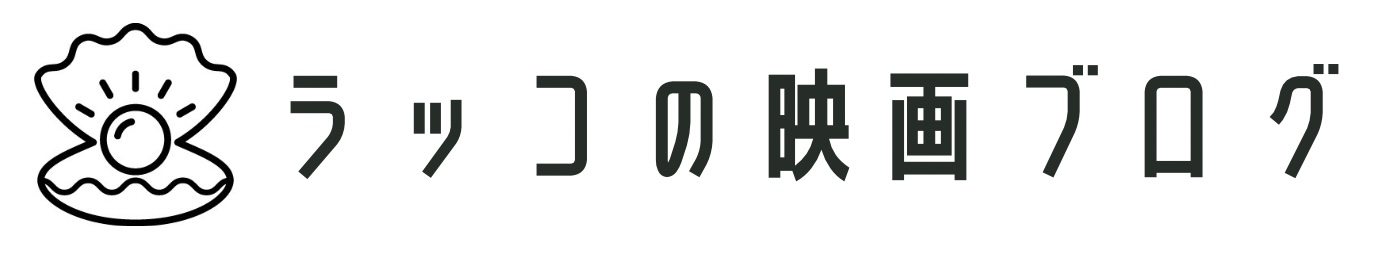
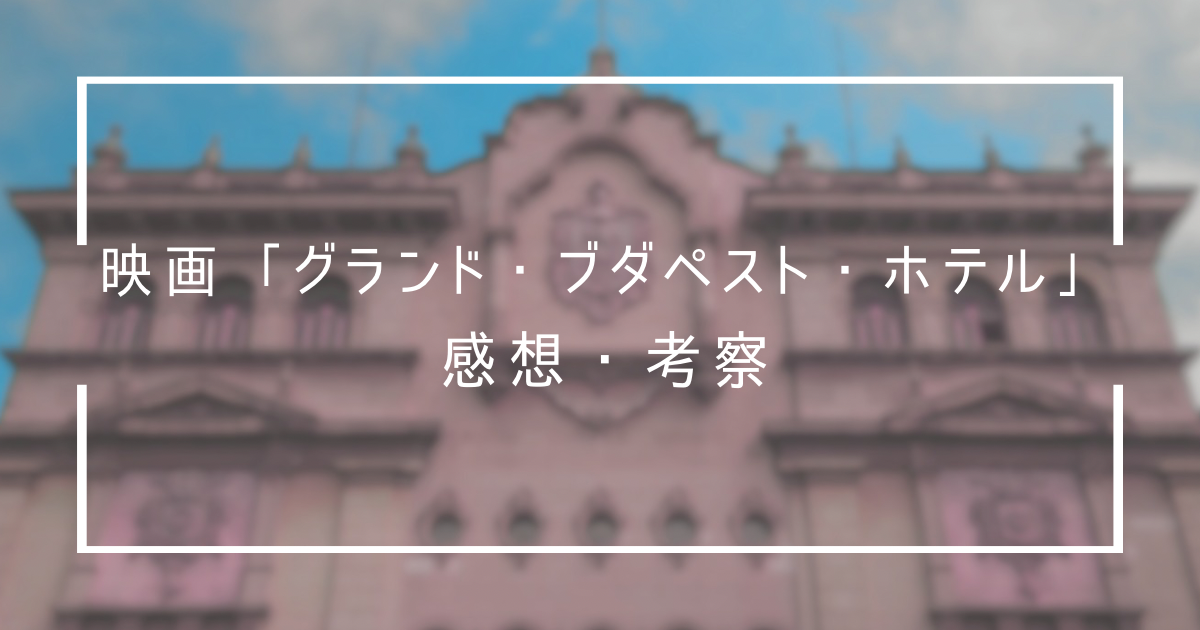

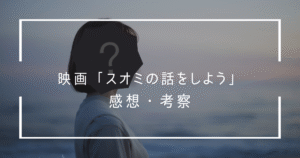

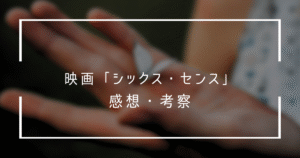
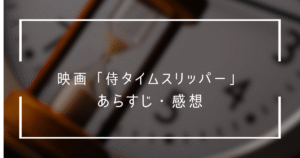
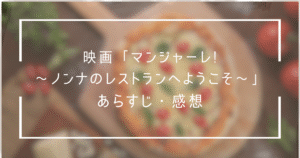
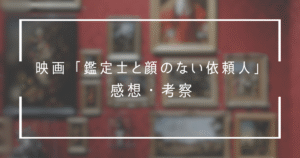
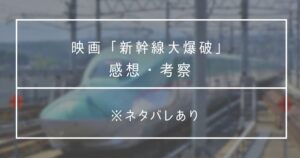
コメント